粟田神社
あわたじんじゃ □京都府京都市


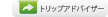


<旅の安全を守る、高台の古社。>
京都の東の玄関口・粟田口に位置する「粟田神社」。古来より旅の安全を守る神として崇敬されてきました。高台にある境内からは、平安神宮の大鳥居をはじめとする岡崎方面の街並みを一望できます。本記事では、粟田神社の魅力やアクセス、実際に訪ねて分かったおすすめ情報などを詳しく紹介します。
所要時間:15〜30分(参拝・見学)
旅の安全を守る、高台の古社。
京都に繋がる街道の出入口で、京の七口と呼ばれた中のひとつが粟田口。東海道でたどり着く京都への入口であり、古来から多くの往来で栄えました。その粟田口で東海道に参道を接しているのが、粟田神社です。創始は876年という古い神社で、後にすぐ隣に境内を接する青蓮院の鎮守社となっていました。交通の要衝である粟田口にあるため、古来より旅の安全を祈願する神として崇敬され、今でもそれは続いています。

京都に繋がる街道の出入口「京の七口」にあり、古くから旅の安全を祈願する神として崇敬されてきた。


参道は東海道に面している。


粟田神社の一の鳥居。
新緑のトンネルが、美しい参道。
東海道、今の三条通から一の鳥居、二の鳥居を過ぎると、参道はやや急な上り坂となります。ここには頭上を覆い隠すように木々が茂っており、秋には見事な紅葉が見られます。訪ねたのは初夏、新緑のトンネルが眩いほどに美しい参道でした。坂道を上っていくと咲いたばかりの紫陽花と、次に神馬の像。そして上りきったところに、粟田神社の神域があります。

二の鳥居を抜けると参道はやや急な上り坂に。訪ねたのは初夏で、新緑のトンネルが眩いほどに美しかった。


「感神院新宮」の扁額が掛かる二の鳥居。


坂道なのは粟田山の麓に位置するため。


参道沿いには紫陽花が咲いていた。


参道沿いに建つ神馬像。
まるで主役のような、桧皮葺の拝殿。
近くの八坂神社の舞殿ように、まず境内の中央に桧皮葺の拝殿があります。多数の奉納された提灯を纏い、まるで主役のような拝殿。その奥に本殿が鎮座します。スサノオノミコト・オオナムチノミコトを主祭神として祀り、威風堂々たる佇まいでどっしりと構える本殿。積み上げてきた歴史が、そこで惜しげもなく語られているように感じます。

創始は876年という古い神社で、後にすぐ隣に境内を接する青蓮院の鎮守社となっていた。


境内の中央にある桧皮葺の拝殿。


拝殿は多数の奉納された提灯を纏っている。


威風堂々たる佇まいでどっしりと構える本殿。


土地の守り神とされる「吉兵衛神社」。
高台の境内からは、岡崎方面を一望できる。
粟田神社は先述したように、坂を上った場所、粟田山の中腹に位置します。麓からは少し高いだけですが、それでも高台になった境内から眺める京都盆地は趣きがあります。特にその景色の中でも異彩を放っているのは平安神宮の大鳥居。町並みから頭ひとつ抜け出した高さ24mの大鳥居は、広いパノラマの眺望の中でもひときわ目立っています。その大鳥居を下から見上げた思い出からすると、逆にそれを見下ろしている粟田神社からの眺望は新鮮そのものです。

境内は高台にあるため、北側に京都盆地の眺望が見られる。町並みから頭ひとつ抜け出した高さ24mの平安神宮大鳥居も見える。


境内は山手の方へと続いている。


大正時代に造られたという煉瓦の擁壁。
興味深く巡る、珍しい境内社。
それと粟田神社には、境内社が数多く鎮座します。伝教大師最澄作と伝わる恵美須神像を祀る「出世恵美須神社」、菅原道真公を祀る「朝日天満宮」、ほかにも聖天社、鍛冶神社、北向稲荷神社、太郎兵衛神社、吉兵衛神社など、あまり聞き馴染みのない珍しい境内社が並んでいて、それらを巡るのも粟田神社の見どころのひとつです。
また毎年10月に行われる粟田祭りでは、神輿に先導するように剣鉾が巡行します。これは祇園祭の山鉾の原形とも言われているもの。境内の宝物殿では剣鉾が見学できます。

粟田神社には境内社が数多く鎮座している。あまり聞き馴染みのない珍しい境内社が並んでいて、それらを巡るのも面白い。


菅原道真公を祀る「朝日天満宮」。


家運隆盛、商売繁盛の神様「出世恵美須神社」。


土地の守り神とされる「太郎兵衛神社」。


雪丸稲荷を御祭神とする「北向稲荷神社」。
photo.
アクセスマップと交通アクセス
■公共交通機関をご利用の場合
- 市営地下鉄東西線「東山駅」2番出口から徒歩約5〜7分
- 地下鉄東西線「蹴上駅」2番出口からも徒歩約7分
- 京都市バス「神宮道」バス停下車、徒歩約3〜5分(5・100系統など)
■車をご利用の場合
- 名神高速「京都東IC」から約5km、車で15分ほど
- 境内の無料駐車場は3台分あり(祭礼日は利用不可の場合あり)
- 祭礼時期は周辺道路が混雑するため、公共交通機関の利用が便利です
■タクシーの場合
- 京都駅(八条口)からタクシーで約15~20分、運賃は1,500円前後
詳細情報
| 名称 | 粟田神社 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区粟田口鍛冶町1 |
| 問い合わせ先 | 075-551-3154 | 粟田神社 |
| 休業日 | - |
| 料金 | - |
| 駐車場 | 無料駐車場 |
| 公式サイト | https://awatajinja.jp/ |
| wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/粟田神社 |
| 食べログ | ー |
| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298564-d7825141-Reviews-Awata_Shrine-Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html |
| LAST VISIT | 202406 |
※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。
情報更新日:2026年1月







